学生のお産見学(分娩見学)、頼まれたら引き受ける?
産婦人科における医学生の医学実習、いわゆる「ポリクリ」。
なかでも「お産の見学」については、個人的に医学生の頃から違和感を抱いていました。
このテーマについては、さまざまな意見があると思います。
・医学生教育のことなんて私には関係ない。恥ずかしい・嫌だから絶対に断るという意見。(主に患者側)
・恥ずかしいなんて甘え。将来の医師育成のためには必要なのでできる限り協力すべきだという意見。(医師側/教育側)
少し両極端な言い方になりましたが…
医師であり、女性でもある私としては、どちらの立場の意見もとてもよく理解できます。
私自身が医学生として産婦人科の実習をしていたとき、「妊婦さんからしたら、学生に分娩に立ち会われるのは嫌だろうな」と感じていました。
なぜなら、当時の実習では、「見学しておくと勉強になるよ」と上級医に勧められ、学生は足元側に立って、赤ちゃんが出てくるところ(つまり妊婦さんの膣)を凝視し、赤ちゃんが生まれたら退室する、というスタイルだったからです。
もちろんお産の臨場感を感じることができたことに対する感謝はありました。
でも、「もし将来自分が出産することになったら、後輩のために学生の立ち会いを受け入れなければ」という義務感のようなものも同時に感じました。そしてそれは、正直あまり気持ちのよいことではないな、とも思いました。
医師である私が“患者”になったとき
医師国家試験に合格し、無事に医師となった私は、その後、結婚と妊娠も経験しました。
「出産までの間、最後の夫婦2人の時間を存分に楽しもう!」とはりきっていたのですが、ほどなくして「切迫早産」と診断され、2ヶ月を超える長期入院に。
当時はコロナ禍で面会も全面禁止。
いくら医師とはいえ、妊娠は初めての経験でわからないことだらけ。
寂しさと不安で、精神的にかなりつらい毎日でした。
入院中は、毎日の回診のたびに、ベッド上で膣洗浄や膣錠の挿入といった処置を受けていました。
カーテンなどの目隠しはなく、ベッド上で下着を脱ぎ、開脚した状態で処置を受ける必要がありました。
そしてその回診には毎日、数人の医学生(男性含む)が見学についてきました。
書面での説明も、口頭での確認も一切なく、「医師である私なら当然受け入れてくれるだろう」という無言の前提のような空気も感じました。
もちろん、“百聞は一見にしかず”という言葉があるように、見て学ぶことの大切さは理解しています。
医学生だったころ、私自身も多くの患者さんにご協力いただき、学ばせてもらいました。
だからこそ、今度は自分が後輩たちに何かを還元しなければ――そんな気持ちから数日は我慢していました。
けれども、漫然と毎日見学にやってくる学生たちに対し、「連日同じ処置を見学して、本当に新たな学びがあるのか?」「私の羞恥心や精神的負担に見合う価値が、その見学にあるのか?」と、疑問に思わずにはいられませんでした。
後日、「連日同じ学生に見学されるのは精神的に負担です」と申し出たところ、一度は謝罪があり、翌日から学生が処置の際に部屋へ入ってくることはなくなりました。
しかしその数日後には、申し送りが徹底されていなかったのか、再び学生が何事もなかったかのように部屋へ入ってきたのです。
もちろん、現場の医療スタッフが日々の業務で手一杯なのは理解しています。
けれども、学生を「とりあえず見学させればいい」というスタンスではなく、
「患者の羞恥心や精神的な負担に見合うだけの学びになっているか?」を、もっと真剣に医療者側には考えてほしいと思いました。
出産時、助産師学生の立ち会いで気づかされたこと
切迫早産での長期入院を経て、いったん退院。
精神的にも少し余裕を取り戻した頃、いよいよ出産のために再入院となりました。
その際、「助産師学生の立ち会いをお願いしてもよいか」と、同意書へのサインを求められました。
一旦退院して気分がリフレッシュされていたこともあり、「まあ、同じ医療者として、後輩たちのために実習に協力してもいいかな」くらいの軽い気持ちで立ち会いを了承し、サインしました。
――結果的に、その学生さんの存在は私にとって、とても心強いものでした。
当時はコロナ禍で家族の立ち会いは当然禁止。
看護師さんや助産師さんたちは常に忙しそうで、頼みたいことがあってもなかなか声をかけづらい。
私は孤独の中で、人生で初めて味わうような痛みに必死で耐えていました。
「誰でもいいから、そばにいてほしい・・・」
「ただ、そばにいてくれるだけでいい・・・」
そんな状況で、ずっとそばにいてくれたのがその学生さんでした。
腰をさすってくれたり、テニスボールで押してくれたり、湯たんぽを用意してくれたり…。
本当にありがたい存在でした。
助産師学生の実習に協力しているつもりだったけれど、むしろ助けられていたのは私の方でした。
これこそが“良い実習”の在り方だと、心から感じました。
産後も、産前の長期入院で筋力が著しく低下していたせいか、赤ちゃんを抱っこして授乳室まで移動するだけで、腰痛がひどく本当に大変でした。
そんな私の様子を見かねてか、哺乳瓶をわざわざ近くまで持ってきてくれたり、授乳クッションを運んでくれたり…。
本当にありがたく、感謝の気持ちでいっぱいでした。
学生さんを受け入れてよかったと心から思えた経験でした。
医学生の「見学だけの実習」に感じる違和感
医学生による分娩の「見学実習」には、以前から違和感を抱いています。
もちろん、そうならざるを得ない背景があることは理解しています。
・医師、特に産婦人科医は多忙で、学生指導に十分な時間を割けない
・産婦人科は訴訟リスクが高く、学生に実践をさせづらい
・参加型の実践中心の実習にすると患者からクレームが来やすい
こうした事情から、とりあえず見学させておこう!と「見学中心」の実習になっているのでしょう。
しかし、妊婦さんは、人生で最も無防備で、痛みと羞恥にさらされる瞬間に、自らの身体を“見せている”のです。これは非常に大きなギブ(提供)です。
その一方で、学生側はただ見ているだけで、患者側に何のリターン(還元)もない――そんな実習になっていないでしょうか?
「見学させてもらいたい」なら「返す姿勢」を
「お産を見なければ産婦人科の魅力も怖さも分からない」という意見はもっともです。
でも、「ただ見学するだけ」で魅力を知ろうとするのも甘いと思います。
妊婦さんが体を張ってお産を見せてくれるのですから、医療者側・学生も何かしら返す覚悟で臨んでほしいと思います。
たとえば:
- 腰をさする
- 声をかけて寄り添う
- 雑用を手伝う
- 飲み物を渡す、買ってくる
小さなことでも、妊婦さんにとっては大きな助けになります。
時には良かれと思った言葉が妊婦さんをイラっとさせてしまうかもしれません。でも、そうした経験も含めて実習で学ぶべきことです。
将来、自身の出産や配偶者の出産の際にもきっと役に立つと思います。
「見学だけだから同意はいらない」は誤り
施設によって違うとは思いますが、助産師の実習では実践を伴うため事前に同意書を取るのが当然である一方、医学生の「見学のみ」では、同意を軽く扱われがちな印象です。
外来や採血の見学であればそれでも問題は少ないかもしれませんが、分娩や内診などデリケートな場面では、しっかりとした同意確認が必要だと思います。
多忙で、紙の同意書が難しければ、口頭でもよいので、丁寧に説明して了承を得ること。
その際、「医学教育のためにご協力お願いします」などとありきたりな言葉でお願いなどすれば、「学生や研修医にみられるなんてイヤ」という妊婦さんが多いでしょう。
でも、「学生ができることはなんでもします。立ち合っている最中、頼み事などは遠慮なくおっしゃってください」など、学生が立ち会うことによるメリットも一言を添えると、患者さんの気持ちも少し変わるのではと思います。
もちろん、拒否する権利があることも明確に示すべきです。
男性にも想像してほしいこと
想像してみてください。
カーテンもない大部屋の真ん中で、激しい痛みの中で大開脚して、強いライトで照らされた局部を何人もの学生に覗かれる。
しかも、その学生はただ足元で突っ立っているだけでなにも助けてくれない。
それでも「全然平気」と言えますか?
「将来の日本の医療のために、医者の卵のために、一肌脱ごう!」と即答できますか?
すっぴんで汗だく、妊娠で体型も大きく変化して、それだけでも家族以外には見られたくない!という女性もいるはずです。
「分娩の見学」とは、女性にとってそれだけの羞恥と覚悟を伴うものなのです。
医学生実習の在り方
「日本の医学生教育のために分娩見学にご協力ください」と妊婦さんにお願いしても、羞恥心や不安から、なかなか受け入れてもらえないのが現実です。
一方で、医学生にとって見学を含む実習が必須であることもまた事実です。
だからこそ、患者側と教育側が歩み寄り、お互いの立場や気持ちを尊重しながら、何が最善かを一緒に考えていくことが大切だと思います。
そのためには教育側が、
- 意味のない漫然とした見学は避ける(特に患者側に身体的・精神的に負担のある診察・処置)
- 分娩見学を了承してくれた妊婦さんには何らかのメリットを還元し、win-winの関係を築く
といった工夫を凝らす必要があると感じています。
さまざまな背景や課題があり、簡単に解決できる問題ではありませんが、私自身の体験が、今後の改善の一助になれば嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
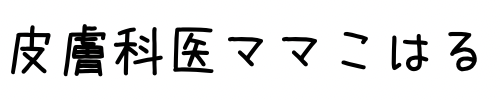
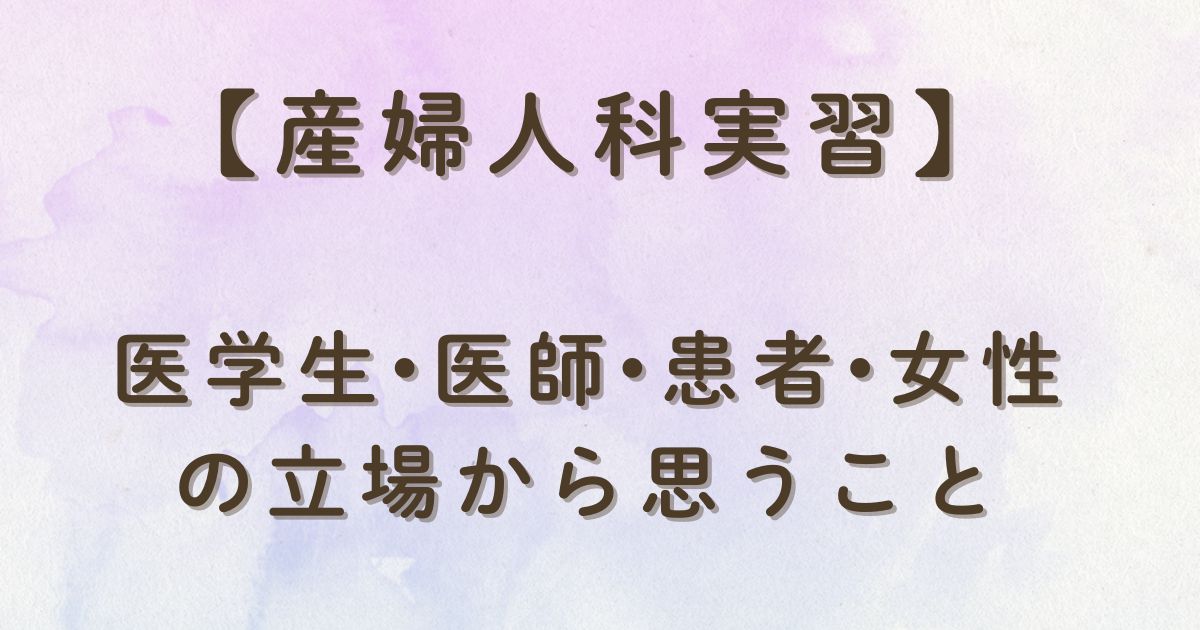
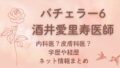

コメント